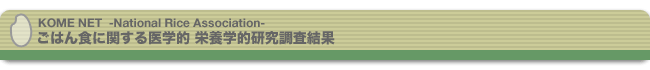 |
|||||||
|
|
|||||||
 |
|||||||
| 東京医科歯科大学 大学院 健康推進歯学分野 教授 川口陽子 研究協力者:品田佳世子、有明幹子、阿部智、杉浦剛 |
|
歯科保健状況と食生活、特に米やごはん食との関連について述べている歯科関連の学術文献25編を検索し、その中の原著論文16編の内容について検討を行った。年齢、歯牙の有無、義歯の使用などと関連させて、食品の嗜好を尋ねる項目の中に、ごはんという項目が入れられている場合が多かったが、ごはんだけを取り上げて歯科との関連性を検討した論文はほとんどなかった。また、ごはんを利用して咀嚼能力機能を評価することは、その調理形態や多様性から咀嚼機能に応じたものを提供できる利点があり、望ましい方法であると考えられた。今後、歯科領域においては、咀嚼機能だけでなく、唾液分泌機能などとの関連性も含め、米やごはん食と口腔や全身の健康との関連を調査していく研究が必要と思われた。 |
|
口腔は食物摂取の入り口にある器官である。口腔の二大疾患であるう蝕や歯周病によって歯が欠損すると、食物を細かく咀嚼できなくなるため摂取食品に制限が生じ、周囲の人と一緒に食事や会話を楽しむことができなくなる場合も多い。このように、歯科疾患が原因で歯や口腔の機能に障害が生じると、私達の普段の食生活は大きく影響を受ける。 現在、歯科領域においては「高齢になっても歯の喪失が10歯以下であれば食生活に大きな支障を生じない」という研究結果に基づき、生涯にわたり自分の歯を20歯以上保って健全な咀嚼能力を維持し、健やかで楽しい生活を過ごそうという「8020運動」が提唱・推進されている。 歯の健康と食生活・食行動との関連について、これまで多くの基礎・臨床・疫学研究が行われ、う蝕と砂糖の関連性が明らかにされてきた。また、近年では、歯を喪失した高齢者の摂食嚥下問題がクローズアップされている。しかし、歯科疾患および口腔機能と米およびごはん食との関連に言及した食生活や食行動の報告は少ない。 そこで、過去15年間に発表された歯科関連の学術文献をレビューして、歯科保健状況と食生活、特に米やごはん食に関して、これまでにどのような研究が行われてきたかを明らかにすることを目的として、本研究を実施した。 |
|
医学中央雑誌刊行会が国内で発行している医学及びその関連領域の定期刊行物を幅広く収集し、各文献毎に書誌事項を収録、さらにマニュアルインデクシングによるキーワードの付与、抄録の作成などの編集作業を行って作成している二次資料データベース「医学中央雑誌基本データベース」から作成した「医中誌Web」「医中誌パーソナルWeb」を利用して、文献検索を行った。対象期間は1987年1月から2001年3月12日までとした。また、大学・学協会・研究所・病院などから発行されている雑誌、営業誌、学会等の会議録、講演集、公共資料などから、歯学雑誌を検索対象に選んだ。検索のキーワードとしては、 |
| キーワードを用いた文献検索の結果、食生活特に米およびごはん食と関連した歯科領域の学術論文は25編あった。その一覧表を資料1に示す。原著論文(16編)は、雑誌名、題名、著者名、所属、抄録を記載し、会議録(8編)および総説(1編)は、雑誌名、題名、著者名、所属を記載した。また、原著論文16編の内容を検討し、記載されていた米およびごはん食と歯科との関連を、以下の3項目に分けてまとめた。 | |||||||||
(1)食品の嗜好、摂取回数について |
|||||||||
|
|||||||||
(2)口腔内状況とごはんとの関連 |
|||||||||
|
|||||||||
(3)ごはんと咀嚼との関連 |
|||||||||
|
|||||||||
|
食生活、特に米およびごはん食と歯科に関する学術論文の数は非常に少なかった。年齢、歯牙の有無、義歯の使用などと関連させて、食品の嗜好を尋ねる項目の中に、ごはんという項目が入れられている場合が多かったが、ごはんだけを取り上げて歯科との関連性を検討した論文はほとんどなかった。 歯や口腔は咀嚼器官であるため、歯科保健状況が悪いと食物摂取が困難になり、食品の選択に偏りが生じ、ひいては健康にも影響がでると考えられる。しかし、日常の食生活は個人の嗜好が大きく関与しているので、単純に歯牙の状況と一つの食品(例:ごはん)との関連を述べることは不可能である。したがって、食生活全体を考えて、ごはんを多く食べるような食生活を送っている人とそうでない人に分けて、栄養バランスをみながら、歯科保健状況や他の生活習慣などを比較してみていくことが必要であると思われた。 ごはんは日本人の主食であり、また、喪失歯数が多くなり、咀嚼機能が低下しやすい高齢者は、ごはんを好む割合が高いことが報告されていた。ごはんは加熱などによりテクスチャーに変化をつけることができ、その調理形態や多様性から咀嚼機能に応じたものを提供できる利点もあり、ごはんを利用して咀嚼能力機能を評価することは望ましい方法であると考えられた。 今後、歯科領域においては、咀嚼機能だけでなく、唾液分泌機能などとの関連性も含め、米やごはん食と口腔や全身の健康との関連を調査していく研究が必要と思われた。 |
制作 全国米穀協会 (National Rice Association)
このホームページに掲載の文章・写真・動画像 および音声情報の無断転載・転用を禁じます。